以下是日本留学网专家介绍的日语惯用语:
あ行
■ 秋風が立つ雨あがり
男女の間の愛情が冷えてしまったようす。 秋 を 飽き にかけて言う。
■ 辺りを払う そばに人を寄せつけないほどに威圧感があり、堂々としている。
■ 委曲を尽くす ものごとの事情について、細かい点まで明らかにする。 委 も 曲 も「詳しい」という意味
■ 潔しとしない 自分の信念に照らし、そういうことをしてはいけないと思うようす。
■ 居住まいを正す きちんと座りなおして、改まった態度になる。 居住まい は、座っている姿勢のこと。
■ 一頭(いっとう)地を抜く 頭の高さだけ抜きん出るという意味で 他より一段と優れていること。
■ 衣鉢(いはつ)を継ぐ 師からその道の奥義を受け継ぐ。 衣鉢 は、師僧から弟子に伝える袈裟と鉄鉢。
■ 言わずもがな 言わないほうがいい。〔用例〕言わずもがなのことを言って、部長を怒らせてしまった。
■ 因果を含める 事情を納得させ、諦めさせる。
■ 慇懃(いんぎん)を通じる 男女がひそかに情を通じる。不倫する。 慇懃 は、親しい交際の意味
■ 有卦(うけ)に入る 時機を得て、よい運にめぐりあう。 有卦」は、陰陽道で幸運の年回りのこと。
■ 倦(う)まずたゆまず 途中で飽きて投げ出したり怠けたりせずに、努力しつづけるようす。
■ 有無(うむ)相通じる 必要とするものを十分に持っている者と持っていない者が、互いに融通しあって満足できる状態にする。
■ 悦(えつ)に入(い)る 思い通りになって、一人でにっこりと喜ぶ。
■ 得(え)も言われぬ (すばらしくて)何とも言えない。
■ 屋上(おくじょう)屋(おく)を架す すでに何かが行われているのに、さらに同じような無益なことを繰り返すこと。
■ おくびにも出さない それらしい素振りも見せないこと おくび は、 げっぷ のこと。
■ 臆面(おくめん)もなく 遠慮もなく平然と ずけずけと。
■ 押し出しがいい 人前に出たときの態度や風采が立派に見えること
■ お為(ため)ごかし いかにも相手のためにするように見せかけ、実は自分の利益を図ること。
■ 押っ取り刀で駆けつける 取るものも取りあえず、大急ぎで駆けつける。危急の際、腰に刀を差す余裕もなく、手に持ったまま駆けつけるという意味
■ 乙に澄ます つまらないことにかかわってはいられないというような、気取った態度をとる。
■ 思い半ばに過ぎる 何かをもとに考えをめぐらし、あることに思い当たる 〔用例〕手紙を読むと、彼の心中について思い半ばに過ぎる。
■ 音に聞く 世間の評判が高く うわさになっている。「音」はうわさの意味。
か行
■ 刀折れ矢尽きる 万策が尽き、どうすることもできない状態に追い込まれること
■ 鼎(かなえ)の軽重を問う刀 権威があるとされている人の実力を疑う。〔用例〕外交問題で、総理の鼎の軽重が問われようとしている。
■ 画餅(がべい)に帰す 計画を立てたものの実現できず、それまでの努力が無駄になる。「画餅」は絵に描いたもち。
■ 裃(かみしも)を脱ぐ 相手に対する気兼ねがなくなり、打ち解けた態度を取る。
■ 干戈(かんか)をまじえる 戦争をする。 干 は 盾 、 戈 は 矛 のこと。
■ 汗顔(かんがん)の至り 顔に汗をかくほどひどく恥じ入ること
■ 間隙(かんげき)を生ずる 人間関係が不和になること。すきまができるという意味
■ 肝胆(かんたん)相照らす 心を打ち明けて親しく交わる。
■ 肝胆(かんたん)を砕(くだ)く 懸命になって、そのことに当たる。
■ 肝胆(かんたん)をひらく 心の内を包み隠さず打ち明ける
■ 間(かん)髪(はつ)を入れず 相手が何かをしたときに、すかさずそれに応じた行動をとるようす。
■ 木に竹を接いだよう 調和のとれない組み合わせや、前後の筋道が通らないことを言う。
■ 驥尾(きび)に付す 才能のない者が、優れた人のあとに付き従い、自分だけではできないようなことをやり遂げる。自分の業績について謙遜して言うときに用いる。青バエも駿馬の尾に取り付けば、一日に千里を行くことができるという意味から。〔用例〕諸先輩の驥尾に付して続けた。
■ 牛耳を執る 同盟の盟主となること。団体や党派の支配的な立場に立つこと 中国で諸侯の同盟の誓いに、盟主となる人が牛の耳をとり、その血を諸侯がすすりあった故事による。「牛耳る」と使う場合もある
■ 胸襟(きょうきん)を開く 心中を打ち明けて話す。
■ 虚を衝(つ)く 相手の備えの不十分なところや油断しているところを攻撃する。
■ 琴線(きんせん)に触れる ちょっとした物事にも反応する。大きな感動や共鳴を与える 琴線 は心臓を包み支える腱と考えられたもの。〔用例〕琴線に触れる言葉。
■ 愚の骨頂(こっちょう) どこから見てもばかげていて、話にならないようす。
■ 謦咳(けいがい)に接する 尊敬する人や身分の高い人に直接会う。 謦 も 咳 も咳(せき)の意味
■ 敬して遠ざける 敬遠する。尊敬しているように見せかけて近づかないでいるが、実は嫌っている。
■ 言質(げんち)を取る 相手から証拠となる言葉を得る。
■ 犬馬の労を取る 自分を犠牲にして相手のために尽くすということを、謙遜して言う言葉 ■ 後顧(こうこ)の憂い 自分がいなくなった後のことのさまざまな気遣い。
■ 功罪相半ばする いい点も悪い点もあり、どちらとも決めかねる。
■ 後塵(こうじん)を拝する 人に先んじられ、後を追う立場になる。
■ 後生(こうせい)畏(おそ)るべし 若い人たちは、将来どんな立派な人になるか分からないので、そのつもりで接しなければならないということ。
■ 浩然(こうぜん)の気 おおらかで、のびのびした気持ち。「浩然」は『孟子』にある語。
■ 糊口(ここう)を凌(しの)ぐ 収入がほとんどなく、その日その日をやっと暮らしていく。 糊口 は、かゆをすする意味
■ 心を汲む 人の気持ちを察する。
■ 事ともせず 特段、大変なことだと思わず、平気で何かをするようす。
■ 今昔(こんじゃく)の感 今と昔を思い比べて、その変化の激しさをいまさらのように感じること。↑ ページトップ
さ行
■ 細大漏らさず 事の大小にかかわらずすべて取り上げる。
■ 沙汰(さた)の限り 言語道断で、是非を論じる必要もないこと。 沙汰 は、是非を議論すること。
■ 歯牙(しが)にも掛けない 相手にしない 問題にしない
■ 下へも置かない 客をとても丁寧に扱うようす。
■ 渋皮(しぶかわ)がむける あか抜けして容姿が美しくなる。
■ 春秋に富む 年が若く、有望な将来がある。
■ 衝(しょう)に当たる 重要な任務を受け持つ。〔用例〕条約調印の衝に当たる。
■ 焦眉(しょうび)の急 (眉が焦げるほど火が近づく意味から)事態が切迫して、一刻の猶予もないこと
■ 曙光(しょこう)を見出す 前途にかすかな希望が見えてくる。 曙光 は夜明けの光のこと。
■ 如才(が)無い 要領がよく、抜け目がない。〔用例〕上司をうまく使いこなす彼は、如才が無い。
■ 緒(しょ ちょ)に就く うまく進み出す
■ 人口(じんこう)に膾炙(かいしゃ)す 広く人々の口にのぼり、もてはやされる。
■ 人後に落ちない 他人にひけをとらない。
■ 人生意気に感ず 人は、金銭や名誉のためでなく、相手の心意気に感じて仕事をするものだということ。
■ 水火も辞さない どのような苦しみや危険恐れず力を尽くそうと決意するようす。
■ 数寄(すき)を凝らす 建物や建具にいろいろな工夫を凝らして風流な感じを出す
■ 正鵠(せいこく)を射る 物事の急所や要点をつく。 正鵠 は的の中心にある黒点のこと。
■ 関の山 なしうる最大の限度 精いっぱい。せいぜい。三重県の関町にある八坂神社の山車が、これ以上のせいたくはないほど豪勢なことが語源になったとの説がある
■ せきらら かくさず、ありのまま。
■ 節を折る やむを得ない事情から、自分の主義 主張を取り下げ、他人に従うこと。
■ 是非に及ばない 事態が切迫し ことの是非を論じている暇がないようす。
■ 前車の轍(てつ)を踏む 前の人の失敗と同じ失敗をする。
■ 千慮(せんりょ)の一失 十分注意をしていたにもかかわらず、思いがけない失敗をすること。■ 象牙の塔 現実から逃避し、観念的な学究生活を送る研究室
■ 相好(そうごう)を崩す 顔をほころばせて、にこやかに笑う。心から喜ぶさま。
■ 糟粕(そうはく)を嘗(な)める 先人の模倣や追従ばかりで、独創性が全くないこと。
■ 底が割れる 話の途中で、うそがばれたり真意を見透かされること。
■ ぞっとしない 好意が抱けないこと。
■ 側杖(そばづえ)を食う 自分と関係のないことで思わぬ災難を受ける。〔用例〕他人のけんかの側杖を食ってけがをする。
た行
■ 多とする 高く評価する。
■ 掌(たなごころ)を返すよう てのひらを返すのがきわめて容易であることから、①物事が簡単にできるようす、②考えや態度が簡単に変わるようす。
■ 矯(た)めつ眇(すが)めつ いろいろと見る角度を変え、丹念に眺めるようす。
■ 端倪(たんげい)すべからず 今後の成行きを推し量ることができないようす。 端 は山頂、 倪 は水辺のことで、物事の限界の意味
■ 旦夕(たんせき)に迫る 死期が迫ること。 旦夕 は朝夕の意味
■ 地歩(ちほ)を占める 地位や立場を確固たるものにする。
■ 等閑(とうかん)に付する たいして重要でないとして、注意を払わない。
■ 同日の論ではない 違いがひどい。比べ物にならない 「同日の談ではない」ともいう。
■ 東西を失う 方角が分からなくなる 途方に暮れる
■ 東西をわきまえない ものの道理が少しもわからないようす。
■ 蟷螂(とうろう)の斧(おの) はかない抵抗のたとえ。「蟷螂」はカマキリのこと。
■ 時を得る 好機を逃がさず、うまく利用する
■ 所を得る 能力にふさわしい職や地位を得る
■ 度を失う ひどく慌てて、どうしてよいか分からなくなる。な
は行
■ 生(な)さぬ仲 血のつながらない親子の間柄。 生さぬ は生まないの意味。
■ 名にしおう 世間で評判の その名も有名な
■ 二世(にせ)を契る 夫婦として末永く連れ添うことを誓う 「二世」は、この世と死後の世界。
■ 寧日(ねいじつ)がない 心の休まる日がない。
■ 軒を争う 家がぎっしり立ち並んでいるようす。
■ 矩(のり)を踰(こ)える その社会の一員として守るべき規範や道徳を無視した行為をすること
■ 肺肝(はいかん)を砕く 目的を達成するために非常に苦心する。
■ 馬齢を重ねる 自ら謙遜して言うのに用い、大したこともせず徒に年を取る意味
■ 半畳を入れる 相手が話をしている途中で、まぜかえしたり茶化したりする。芝居小屋で 役者の演技に対する不満を表すために 観客が敷いていた半畳のござを舞台に投げ入れたことから。
■ 万難を排する あらゆる困難や障害を押しのける。
■ 蛮勇をふるう 無鉄砲に勇気をふるう。
■ 範を仰ぐ 手本として見習う。
■ 引きもきらず 次々に絶え間なく。
■ 顰(ひそみ)に倣う 顰 というのは、眉のあたりに寄るしわのこと。昔、中国の越の西施という美女が病に苦しみ顔をしかめていたのを美しいとして、多くの女たちがその表情のまねをしたという故事から、いい悪いの見境なく、他人のまねをすること。
■ 平仄(ひょうそく)が合わない 話のつじつまが合わない。
■ 無聊(ぶりょう)をかこつ 不遇な状態にあるわが身を嘆く 「無聊」は暇で時間を持て余す意味
■ 方図がない どこまでも際限がない。 方図 は際限の意味
■ 忙中閑あり どんなに忙しい時でも、ふとした折にちょっとした暇ができるものだ。ま
や~行
■ 間尺に合わない 損になる。割に合わない
■ 末席を汚(けが)す 仲間となり、その地位や職などにいることを謙遜して言う言葉
■ 眦(まなじり)を決する 怒りなどで目を大きく見開く。 眦 は 目のしり の意味
■ まんじりともしない 一睡もしない。
■ 微塵(みじん)もない 少しもない。「微塵」は、ごくわずか、細かいほこりの意味
■ 水際(みずぎわ)立つ 飛び抜けて見事さが目立つ
■ 耳を聾(ろう)する 飛び抜けて見事さが目立つ
■ 身を持する 誘惑に負けたり怠惰に流されないように、厳しい生活態度を取りつづける。
■ 名状(めいじょう)しがたい 言葉で言い表せない。
■ 目先が利く 先を見通し、気転のきいた行動がとれる。
■ 目もあやに 先を見通し、気転のきいた行動がとれる。
■ 面目を一新する 古いものが改まり、すっかり新しくなる
■ 蒙(もう)を啓(ひら)く 無知な人々に必要な知識をあたえる。啓蒙する 蒙 は、知識がなく道理に暗いこと
■ 雪を欺く 雪のように真っ白いようす。
■ 誼(よしみ)を通じる 打算的な目的をもって、親しい関係を結ぶ。
■ 余所(よそ)に聞く 自分とは無関係のこととして、聞く
■ 埒(らち)もない ばかばかしい。
■ 累を及ぼす 自分がしたことが原因で、他人に迷惑をかける。
■ 坩堝(るつぼ)と化す 集まった大勢の人々が興奮して 混乱状態になること









 疫情下英语系留学新选择—日本...
疫情下英语系留学新选择—日本...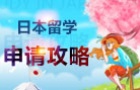 日本留学申请攻略
日本留学申请攻略 日本语言学院申请技巧
日本语言学院申请技巧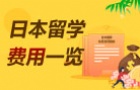 日本留学费用一览
日本留学费用一览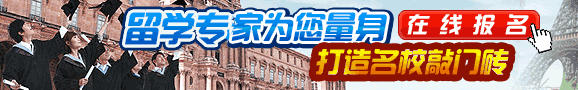






 东京大学
东京大学 九州大学
九州大学 北海道大学
北海道大学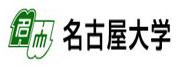 名古屋大学
名古屋大学 神户大学
神户大学 筑波大学
筑波大学

